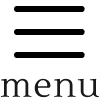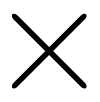ブドウ畑について
畑の概要
農花の畑がある小諸市糠地地区は、千曲川の右岸、浅間山や黒斑山の山塊に連なるほぼ南向き斜面に広がっています。糠地を代表するワイナリー、テールドシエルさんを筆頭に、すでに数人のワイン生産者が入植しており、千曲川ワインバレーの中でも新しいワイン産地として定着しつつあります。標高は約700~950メートルと高く、小諸の市街地に住む人々から見ると、「昔、遠足で行ったなあ~」という「山」エリアだそうです。
農花の畑はの標高は、およそ標高850メートル。日当たりがよく日照時間が長い一方、冬はマイナス10度以下になることもざらです。温暖化が進む昨今、長野の高地は、本州に残されたブドウ栽培の適地のひとつです。
ヴィンヤードは約30a、小さな畑です。700本ほどのブドウ樹を植えています。
赤品種:カベルネフラン中心(メルロー、カベルネソービニョン少量)
白品種:シャルドネ、ミューラートュルガウ、ソービニヨンブラン、ケルナー、バッカス、フルミントなど。(プチマンサン、ゲヴェルツトラミネール、リースリング、ルーサンヌなども少量)
ヴェレゾン(色づき)が始まったメルロー
2018年冬に訪れたアルザスのブドウ畑の仕立てをまねてみたカベルネフランの区画

雨除けのため、ロウでコーティングされた傘をかけます
早春のブドウ畑。ヒメオドリコソウなど、自然のお花畑が広がります。標高が高く寒いエリアなので、ブドウ樹は藁を巻かれて越冬します。
農花の畑の方針
①除草剤を使わないこと
いろんな草が生えてくるのは自然なことなので、使いません。
ブドウの木が大きくなってきたので、草をはやしていても負けなくなってきました
2024年は、6月以降、一切草刈りをやめる列をつくり、草生栽培にもチャレンジしてみました。草刈りをしないほうが、した列よりも背の高い草が抑えられるという好ましい結果になりましたが、長雨が続くとカビ病のリスクが高まって苦労しました。
2024年7月末ごろ。ちょっと生やしすぎたか
日本は高温多湿で、多くの植物にとっては天国のような土地です。ブドウを守るためには、草刈りで風通しを良くしたり、虫が増えるのを防いだり、ブドウに病気をもたらす菌の宿主になるような植物を除去していくのは、日本で農業をやる上では欠かせません。しかし、同時に、さまざまな植物が畑に生えていること自体が、夏の高温時に温度を下げてくれたり、雑草の深い根っこが土を柔らかくしてくれたり、害虫を食べるカエルたちの住処になったり、枯れた後には有用微生物たちの餌になってくれたりと、ブドウへのメリットをもたらすこともたくさんあります。
カエルたちは、畑作業のお供です
草との戦いは果てしないですが、草を仲間にもしたい。そのバランスと着地点を見つけようと毎年苦戦しています。
②肥料をやらないこと
ブドウ畑の前は、飼料用のトウモロコシが栽培されていました。
窒素過多の部分もあったので、2018年、開園の時に石灰とバークたい肥を撒いて以来、まったく肥料をやっていません。牛糞などの有機肥料も、一切やりません。もともとのヴィニフェラ系ブドウの産地は、乾燥して瘦せた土地なので、窒素はできるだけ抜いたほうがいいと思っています。徒長を抑えたり、枝が暴れたりしないようにするためです。
ブドウの搾りかすや梗、くん炭などを撒くことはあります。枯草菌の宝庫の稲わらは、毎年、藁巻きに使った後、株間に敷き詰めています。
③必要最低限の農薬で畑を維持すること(4~5分の1程度の散布量)
農薬には、いろいろな種類があります。化学合成農薬以外にも、有機JAS認証で認められているボルドー液やマシン油、食用の重曹や酢、昆虫や微生物などを利用した生物農薬も、畑に撒けば「農薬」になります。
畑を始めた当初、有機認証(オーガニック)を目指し、認証内で認められた農薬のみ(ボルドー液や石灰硫黄合剤)で栽培することを目標としていましたが、現在では、化学合成農薬も休眠期・開花の時期の要所で使いつつ、全体の農薬散布量を減らす方向で試行錯誤しています。
もともと、背負い式の手動散布機で、すべて手散布(!)で防除しているので、1回の散布量は、推奨されている量の5分の1程度です。
どうやったら少ない農薬で、効率的にブドウを守れるか、いろんな本などを読みつつ、少しずつ、やり方を研究しているところです。
④多様な品種を混植すること
当初は、畑に合った品種は何かを探るつもりもあり、少量多品種で、さまざまなブドウ苗を植えた部分もありました。
しかし、そうしているうちに、毎年の天候に応じて、「今年はバッカスが良く実った」「今年はケルナーがいい房が採れた」というように、品種によって実り方に違いが出てくることがわかってきました。結果的に、ビンテージごとのブレンドで、マセラシオンやロゼなど、毎年、さまざまなテイストのワインができています。
これまで出してきたワインは、どれもフィールドブレンドですが、配合が少しずつ違います
大手のワインメーカーや、ブランドもののワインでは、年毎の味やクオリティの均一性は大事なことですが、その年だけの一期一会のワインを作るのも、農花のような極小ワインメーカーならではの面白さかなと今では思っています。
2020年の初収穫の時から醸造してくださってきた、テールドシエルの醸造担当・桒原さんの、「ワインはその年その年のブドウを映すもの」という言葉に、大きな影響を受けています。
⑤あまり無理しないこと
これは私事で、皆様にはどうでもいいことですが(笑)、一人で作業することが多いので、いろいろ無理しないことにしています。
無理しすぎると辛くなるので、「楽しいなあ」「きれいだなあ」と思えるくらいのほどほどな作業量(←ここ大事)をモットーにしています。
ワイン醸造の方針(委託醸造)
①醸造家さんの判断を信頼すること
「餅は餅屋」という言葉がありますが、醸造に関しては、その年のブドウを見て、一番いいと思う方法で醸造してくださる醸造家の判断を信頼しています。「こういうワインにしたい」という完成図を頭で思い描くのではなく、その年採れたブドウで、一番いいワインにすることがモットーです。
初めからそうだったというよりは、これまで、テールドシエルの桒原さん、ツイヂラボさんのタカさんという二人の醸造家とワインを作る中で、醸成されてきた考え方です。
②野生酵母を使い、必要な場合には保存料を少量添加すること
これまでに作ったワインはすべて野生酵母のみで発酵したものです。それは今後も変わらないと思います。
ブドウの皮についた酵母だけで発酵します
瓶詰時には、亜硫酸をほんの少量入れることが多いです。少しでも劣化のリスクを避けるために、無添加にはこだわりません。